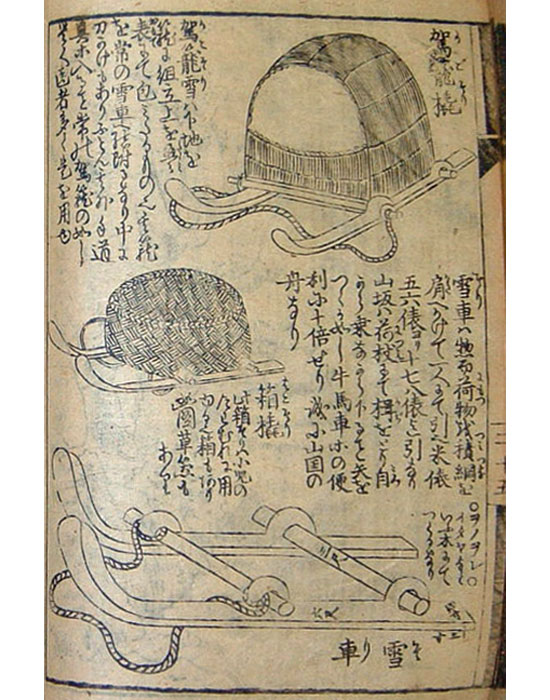解読文
駕籠橇(かごそり)
駕籠雪(かこそり)は、下地を籠に組立、上を畳表(たゝみおもて)にて包みたるもの也、其籠を常の雪車へ結附るなり、中に刀かけもあり、ふとん其外手道具等入ること常の駕籠の如し、常々医者多く是を用ゆ
雪車(そり)
雪車(そり)は、惣而荷物(にもつ)を積(つみ)、綱(つな)を肩(かた)へかけて一人にて引也
米俵五六俵ヨリ十七八俵迄引なり、山坂は荷杖(につえ)にて楫(かぢ)をとり、自(みつ)から乗なから下ること矢をつくか如し、牛馬等の便利に十倍せり、誠に山国の船なり
○ヲノヲレ○
イタヤなといふ木にてつくるなり
箱橇(はこそり)
此箱そりは、小児のたわむれに用ゆる也、箱もあり、北国草籠もあり
解説
用語
- 下地:土台
- 結附る:結び附ける
- 惣而:総じて
- 矢をつくか如し:放たれた矢のようだ
- 十倍せり:十倍である。サ変動詞「せ」+完了の助動詞「り」
- ヲノヲレ:雪車(そり)は、斧折れ(カバノキ科の落葉高木)や板屋楓(カエデ科の落葉高木)などの木で作る。
- 此箱そり:この箱そり
MEMO
『旅行用心集』奥州・越後の寒い国についての文脈の中で、ソリが紹介されています。解読文は上記用語を参照いただければ、現代語訳なしで意味は通じると思います。ほっこりと言うべきかアバンギャルドと言うべきか、どちらにせよ乗ってみたい乗り物ばかりです。
史料情報
- 表題:旅行用心集/文化7(1810)
- 八隅芦庵 著、彫工:佐脇庄兵衛・同 伊三郎、出版元:須原屋茂兵衛・須原屋伊八
- 埼玉県立文書館寄託 小室家文書3361
- 当サイトは同館から掲載許可を頂いてます。
- ※無断転載を禁止します。